
「メンタルを鍛えるのはアスリートや心の病を抱えた人だけ」――そんなイメージ、ありませんか?
実は今、“心の筋トレ”として、もっと日常に近いメンタルトレーニングに注目が集まっています。
感情の波に振り回される日々から抜け出し、自分の機嫌を自分で取れるようになること。それこそが、これからの時代をしなやかに生きる鍵になるのかもしれません。
そんな未来を見据えて「メンタルトレーニングの義務教育化」を目指すのが、2025年に起業したばかりの中里さんです。

「といえば」ってどういう意味?ユニークな社名に込めた3つの想い
「株式会社といえば」というインパクト抜群の社名。思わず「えっ?」と聞き返してしまうこの社名には、3つの意味が込められています。
「“メンタルといえば中里”と覚えてほしいというのがひとつ。もうひとつは、誰もが人生を変える“問い”に出会える場所にしたいという想い。そして最後にToy=おもちゃ。大人にもピュアに喜べる瞬間を届けたいと思って遊び心も込めました」
キャッチーだけど中身はとても真面目。社名ひとつ取っても中里さんの熱い想いが滲んでいます。

法人化したのは、「本気で文化にしたい」から
個人事業主として活動していた時期が長かった中里さん。起業を決意したのは、想いを形にするためでした。
「日本の義務教育にメンタルトレーニングを入れたいんです。今、メンタルトレーニングを学べる場が学校にも、社会にもほとんどない。だから、子どもの頃から“自分の心との付き合い方”を学べる世界にしたいんです」
「ただ、その文化を根づかせるには、個人の活動では限界がある。経営者の方々とご一緒する機会も増えた中で、“個人事業主”という肩書きでいるのが、なんだか逃げているように感じてしまって」
法人化によって堂々と想いを伝えられるようになったといいます。
学生時代に目指していた王道から外れて
――やりたいことに本気で向き合ったからこそ出会えた別の道
もともとはスクールカウンセラーを目指していた中里さん。
札幌の高校を卒業後、心理学を学ぶために東京の大学へ進学します。
公認心理師を目指し、大学院進学を前提とした道を一直線に進んでいました。
ところが、研究計画書を書く段階になって、自分が本当にやりたいテーマに違和感を抱きます。
「病気の人を対象にした研究ではなくて、健康な人がもっと楽に生きられる方法とか、そういう研究ばかりが浮かんできたんですよね。自分がやりたいのは、臨床で“治す”ではなくて、“支える”とか“予防する”ほうかもしれないと思いはじめたんです」
大学院の心理学の先生たちに相談するも「うちでは扱えない」と門前払いの連続。
悩んでいたときに出会ったのが、当時ラグビー日本代表の五郎丸選手に帯同していたメンタルトレーナーの記事。
「これだ!」と感じ、すぐに動き出します。 “メンタルトレーナー”を名乗る人たちに片っ端からDMを送り、その中で出会った一人の師匠の考え方に強く共感。大学院進学をやめてこの道に進むことを決意しました。

現場で見えた“心の筋トレ”の可能性
「僕がこの世界に飛び込んだ時、メンタルトレーニングはアスリートがほぼ対象であって、一般の方を対象としたものは多くなかったんですよね」
ということからわかるように、最初はやはりスポーツの現場が中心だったそうです。
実業団や学生チームに対して無償でも構わないと売り込み、経験を積みました。
転機は、「これ、経営者にも効くんじゃない?」という人材紹介会社の社長の一言。アスリートに向けていた“心の筋トレ”が、経営者や組織にもハマると実感し、活動の幅が一気に広がります。
現在は、以下の3つを軸に企業向けの支援を展開中。
- 1on1の代行
- 企業研修
- メンタル視点での組織コンサルティング
従業員の声を拾い、改善策を提案・実行。評価される立場ではない“第三者”だからこそ、素直な本音も引き出せるのが強みです。
「辞めない組織」のつくり方
印象的な事例として、中里さんが語ってくれたのが、ある企業での取り組み。リーダー職が次々辞めていく組織に入り込み、半年で離職ゼロを実現しました。
何をしたかというと、新人社員のオンボーディングに半年間の「並走プログラム」を設計。
最初は“安心の土台”づくりから始まり、徐々に“自分と向き合うトレーニング”へ、そして“自立”のフェーズへと進める流れです。
「心理的安全性がないと、どんなに制度を整えても心は定着しない。だからこそ、まずは“ここにいていい”って思える安心感をつくることが先なんです」
既存社員や中間管理職へのサポートも充実しています。1on1でその人の“あり方”や“クセ”と向き合いながら、心の弱点に直接アプローチ。なかでも中間管理職は「特に病みやすいポジション」だそうです(笑)
“全員が活きる”組織を、本気でつくりたい
「この子はメンタル弱いから戦力外でいいや、っていう風潮があるじゃないですか。僕はそれが本当に嫌なんです」
中里さんが目指すのは、「全員が活きる組織」
一部の優秀な人だけが評価される場所ではなく、正しいメンタルトレーニングを通じて誰もが成長できる場所。

カウンセラーとメンタルトレーナーの違い
「似ているようで、全然違うんですよ」と中里さん。
「カウンセリングは“心のリハビリ”。何かしらの精神的な困難を抱えている人が対象で、「ゼロよりマイナスの状態を回復させる」支援です。一方、メンタルトレーナーは“心の筋トレ”。健康な人が、よりよく自分を鍛えるためのものです」
対象も方法も、まるで違います。
「例えば“緊張します”という人がいたら、理論と対策をセットで伝える。“こうやって整えていこうね”と具体的なトレーニング方法を提供して実践を促す感じです。トレーニングでコントロールできることを知ってもらうんです」
筋トレと同じく、正しいやり方を知れば人は変われる。それを広めるのが、自分の使命だと語ります。
「自分をご機嫌に保つ」ことがプロとしての責任
組織に入り込み、個人に寄り添い、変化を起こす。メンタルトレーナーの仕事は、実はかなりのエネルギーを消費します。
「だからこそ、自分自身のコンディションはすごく大事にしています。自分が整ってないと、絶対に人を支えられないですからね」
家族と過ごす時間、友人と遊ぶ時間、そして趣味の時間。どれも“自分をご機嫌に保つ”ための大事な時間だといいます。
「何者かになりたい」その一心で走っている
ビジネスとしてこの仕事を続けるのは、正直かなり大変だといいます。
信頼していた人に裏切られたり、お金のことで悩んだり――。
それでも続けている理由は、たったひとつ。
「普通の人でいたくない。北海道にメンタルトレーナーっていうよくわからない仕事をしているヤツがいるんだって思われたいんですw」
心からやりたいと思えるのはこれだけ。
中里さんにとって、メンタルトレーナーは“生き様”そのもの。
「まだメンタルトレーニングのことを知らない人に届けたい。日本でこの分野を切り拓く第一人者になれたら最高ですよね。…そのためには応援してもらえる人にならなきゃと思っています」

編集後記
メンタルトレーナーという仕事に出会う前。元々カウンセラーを目指していたという中里さんがなぜその道を志したのか、気になって深掘りしてみました。
高校3年生の頃、なんとなく札幌市内の大学に進学するつもりだったものの、自分が本当にやりたいことがわからず、迷っていたそうです。そんなとき、国語の先生に紹介されたのが、河合隼雄さんの『こころの処方箋』という一冊でした。
“心の専門家”という存在に初めて触れ、「もしこんな人が学校にいたら、救われる人がきっともっといたはず」と感じたという中里さん。そこから一念発起し、進学先を白紙に戻して心理学を学ぶために東京の大学へ進む決断をします。
その背景には、人生を変える本との出会いと、やりたいことに真剣に向き合う彼のストイックさがありました。
一方で、「僕と出会った人は、なぜかみんな元気になっちゃうんですよね!」と笑いながら話す姿には、自然と周りを明るくする人柄がよく表れていました。今後の中里さんの活躍が楽しみですね。どのような未来を描いていくのか、ますます注目していきたいです!
取材・文:michimichi編集部員A.T
プロフィール
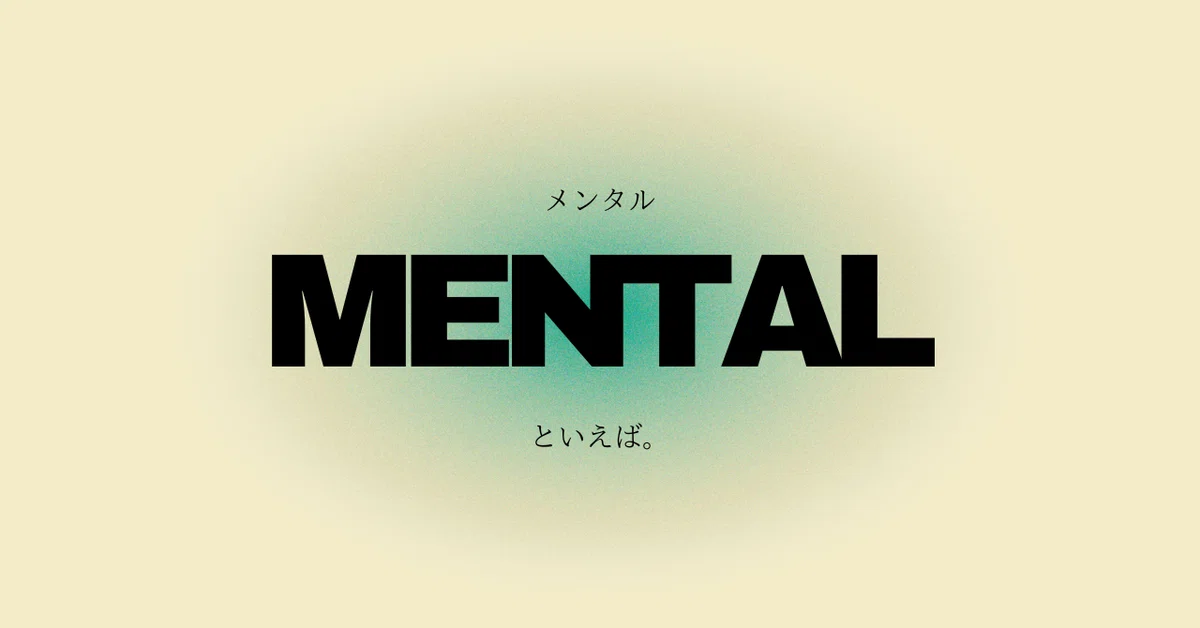
ライター情報
この記事をシェア
URLをコピーしました!
-
前のコンテンツ
なにやら弊社の広報が忙しそう。「出張人事図書館」ってなんだ。 -
次のコンテンツ
がんばれ、ビジネスパーソン